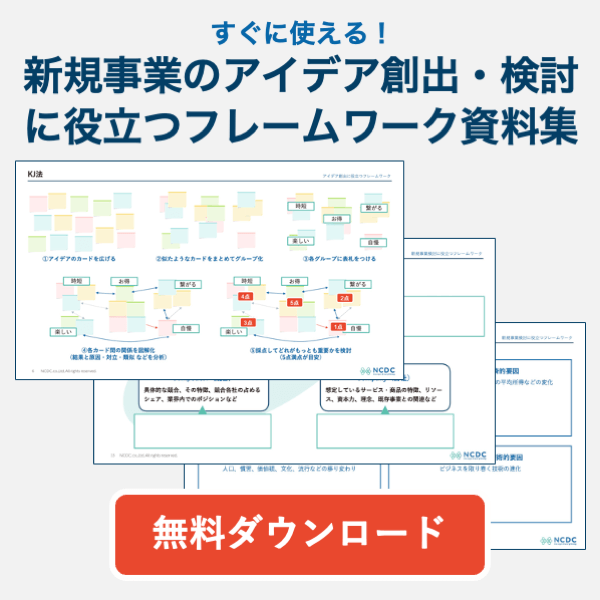2024年12月19日にオンラインセミナー『思いつきに頼らない新規サービスのアイデア創出 再現性のある手法の解説』を開催いたしました。
この記事では当日用いた資料を公開し、そのポイントを解説しています。
目次
はじめに
今回ご紹介するいくつかのフレームワークを活用することで、思いつきに頼らないアイデア出しが可能になります。ただし、フレームワークを使えば必ず良い新規サービスのアイデアが生まれるわけではありません。
例えば、一見良さそうなアイデアでも、自社の強みとは全く別の技術が必要であったり、大きな社会課題の解決に貢献できそうなアイデアでも、実行するには専門知識が足りなかったりと様々な問題に直面することがあります。
そのため、アイデア出し自体が思いつきにならないことはもちろん、自社の強みや自社に適したビジネスモデルの理解、適切なテーマの選定などが新規サービス検討のベースにあることが大切です。この点を念頭に置いて解説していきます。
既存ビジネスとの連続点を考える
新たなビジネスモデルは、非連続では生まれません。ビジネスモデルを考える上で重要なのは、既存ビジネスとの連続点、延長線上で新しいものを見つけていくことです。
例えば、以下の6つのパターンが考えられます。
1. ターゲット顧客が同じ
ひとつめは既存ビジネスですでに獲得している顧客に対し、新しい価値やサービスを提供するパターンです。

上図の例は、航空会社が、出張のために飛行機を利用するビジネスパーソン向けに新しくホテル事業を始めたケースです。航空会社は早朝便の利用促進などの効果が見込め、顧客は近くにホテルがあることで前泊の利便性を享受できます。ホテル側も一から集客する必要がないため、三者ともに良いビジネスモデルと言えます。
2. バリューチェーンが並ぶ
続いては、「バリューチェーンが並ぶ」パターンです。これは、既存ビジネスの商流を活かして効率的に事業を立ち上げるものです。

分かりやすいのは、ITコンサルティングを手がける会社が、その後続のシステム開発まで行うケースです。上流のみを行うコンサル会社は開発以降の工程を他社に引き継いだり、外注したりしますが、一連のバリューチェーンを一貫して自社で行うよう体制を整えることで、開発や運用の案件を自然な流れで得られるようになります。
同じパターンでもうひとつ、エアトリをご紹介します。宿泊予約に加え、旅行における移動手段(飛行機、バス、レンタカー)の予約、さらには海外で使えるWi-FiルーターやeSIMの貸出も行うなど、旅行に行ってから帰ってくるまでの流れを一元的にサポートするサービスとなっています。
3. 回転率を高める
3つ目は、「回転率を高める」パターンです。これは、在庫や設備・資産などの空きを減らし、それらを新しい価値として提供するものです。

例えば、バーの営業で考えると、稼働している夜間の営業時間以外は利益を生み出しませんが、家賃はかかっています。この日中の空きを埋めるため、昼間に定食屋さんをやりたい別の人に店舗を貸し出すことで、場所代だけでも利益を生み出すことができます。
世界有数のクラウドサービスとなったAWS(Amazon Web Services)もはじめはこのパターンでした。元々AmazonのECサイトでは、ブラックフライデーのようなピーク時に備えて大量のコンピューティングリソースを確保していましたが、ピーク時を過ぎるとそのリソースが余ってしまうという課題がありました。そこで、余ったリソースを貸し出す形で収益化できないかと考えられたのがAWSの始まりと言われています。今では単なるリソースの貸し出しではないAI等の多彩なサービスを提供し、クラウドサービスプラットフォームのトップシェアを誇っています。
4. 独自技術を転用する
4つ目は、「独自技術を転用する」パターンです。既存の事業で培ったコアな技術やノウハウを、別の用途や業界に展開するものです。

事例としては、富士フイルムの例が挙げられます。フィルム内部に正しく粒子を配置するナノテクノロジー技術、写真をきれいに保つためのコラーゲン研究、写真の色あせを防ぐための抗酸化技術や、光の制御をはじめとした光学技術といった写真にまつわる独自技術を、一見全く異なる基礎化粧品に応用した事例です。
デジタルサービスの例では、クラウド名刺管理サービスのSansanから生まれたBill Oneが挙げられます。Sansanで使われている書面(名刺)の情報を正確にデジタルデータ化する技術を、請求書データの読み取りにも転用できないかという発想から生まれたサービスです。
5. 似た世界を転用する
5つ目は、「似た世界を転用する」パターンです。これは、既存のビジネスモデルと類似した業界や市場に展開するものです。

例としては、上図のように人間向けグッズをカスタマイズしてペット向けとして販売するケースが挙げられます。
ライドシェアサービスのUberから生まれたUber Eatsもこれに該当します。Uberは元々人を目的地まで運ぶライドシェアサービスでしたが、「輸送する」「配送する」という共通項を出前配達に転用することでUber Eatsが誕生しました。
6. マッチングする
最後は、「マッチングする」パターンです。

例えば、複数社からまとめて見積もりを取れるサービスが挙げられます。発注者が個別に各開発ベンダーに見積もりを依頼し、やり取りを行う従来のフローを、マッチングプラットフォームが仲介することで、発注者は連絡窓口を一本化できます。開発ベンダー側も依頼を待つだけではなく自分たちで案件を探しに行けるメリットが生まれます。
ここまで既存のビジネスから新たなビジネスモデルを生み出す6つのパターンをご紹介しました。こうした知識はある程度頭に入れた上で、新規サービスの検討に取り組むのがお勧めです。
アイデア発散のための5つのフレームワーク
ここからが本題です。思いつきだけに依存せずアイデアを沢山出していくためのフレームワークを紹介します。
アイデア発散のコツ
はじめにアイデア発散のコツを4点お伝えします。
- 質より量:1つのアイデアの説明や深掘りに時間をかけ過ぎないこと。良いアイデアが思いつくと、それの実現性や意義などについて語りたくなってしまいますが、質は後で高めるので、先ずはたくさんアイデアを出しましょう。
- 人のアイデアを否定しない:突拍子もないアイデアも受け入れること。当たり前と思われるかもしれませんが、意外と多いのが「それは現実的じゃない」「無理でしょ」と、出されたアイデアを否定してしまうケースです。注意していてもつい否定してしまうことがあるため、意識しましょう。一見イマイチでも、視点を変えると良いアイデアに化けることがあります。
- 人のアイデアに便乗する:真似する、誇張する、合体する、言い換えるなどしてみること。受け入れがたいアイデアが出たとしても、どうすれば良いアイデアに転換できるかという視点で考えましょう。行き詰まってアイデアが枯渇してきたら、積極的に便乗して広げましょう。
- 会話する、でも一人が喋りすぎない:一人で黙々とアイデアを出すのではなく、喋りながらアイデアを出すこと。黙々と作業するだけでは、自分の意見の範疇を超えることはできません。誰かのキーワードをヒントにしたり、自分が積極的に話して誰かのヒントになったりするよう、会話をしましょう。ただし、上司や先輩などが喋り過ぎてしまうケースもあるため、注意しましょう。
これらのコツを押さえて、5つのフレームワークをご紹介します。

アイデアをゼロから生み出すもの、アイデアをひとひねりして転換するもの、キーワードを拡げるものという観点にまつわる5つをご説明します。
1. マンダラート
一つ目は、「マンダラート」です。大谷翔平選手が目標設定に使ったことで有名になったので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。テーマから連想するキーワードやアイデアを出していくフレームワークです。キーワードから更に連想してキーワードを出していくことで、特定の視点に偏らず幅広く発想することができるのが特徴です。

手順は以下の通りです。
- まず中心にテーマ(例:健康)を置きます。ここは「〇〇ができるアプリ」や「〇〇を解決するサービス」のようなテーマでも構いません。そして、このテーマから連想するキーワードを周囲の8マスを埋めるように書き出します。
- ステップ1で連想したキーワードを中心にして、さらにキーワードやアイデアを出し(例:習慣、規則正しい生活、早寝早起きなど)、周囲のマスも埋めていきます。
2. 635法
二つ目は、「635法」です。6名のメンバーが3個ずつのアイデアを書き出し、5分ごとに隣のメンバーにバトンタッチしながらアイデアを出していくフレームワークです。635法という名前は、「6名」「3個」「5分」から名付けられました。
自己主張が苦手なメンバーでも、前の人のアイデアに便乗しやすいため、アイデアが出てきやすいという特徴があります。

手順は以下の通りです。
- まず、1枚の紙に3つのアイデアを5分以内に書き出し、その紙を右隣の人に回します。
- 左隣の人から受け取った紙に書かれたアイデアを参考にしながらさらに3つアイデアを書き出し、また右隣の人に紙を回します。これを1周するまで繰り返します。
これにより、6枚の紙に18個のアイデアが書き出され、合計108個のアイデアが生まれます。30分程度で108個のアイデアが生まれるため非常に効率的で、事前の学習も不要なため取り組みやすいフレームワークとなっています。
アイデアの転換と拡張
ここまでで、マンダラート(9×9=81個)と635法(6×18=108個)で、最低でも189個のアイデアが生まれているはずです。テーマによってはマンダラートが複数枚あったり、テーマの数だけ635法を行ったりすることで、さらに多くのアイデアやキーワードが出ているでしょう。
これらを元にしても良いですし、全く新しく考えても良いですが、3つ目に紹介するのは次の「常識を疑え」というフレームワークです。
3. 常識を疑え
今から取り組もうとしているテーマ、現状のビジネス、サービスを提供しようとしている業界の中で常識となっていること、いわゆる「固定観念」を洗い出します。その常識や固定観念を「逆転」させてみて、その逆転させたアイデアからサービスを考えていくのがこのフレームワークです。

手順は以下の通りです。
- まず、常識になっている考え方や固定観念を洗い出します。
- 常識を逆転させてみます。
- 逆転させたアイデアからサービスを考えます。
例えば、「体重計は細かく正確な数値まで測れるべきだ」「体重計で体脂肪率なども測れる高機能なものが良い」という常識があるとします。
これを逆転させてみると、「正確な数値は不要で、測定できる数値もざっくりで良い」となります。この逆転させたアイデアをどうすれば良くなるか考えると、「体重の数値は測定できないが、増えたか減ったかの傾向だけが測定できる」というものが考えられます。これであれば、数値にとらわれて一喜一憂せず、長期的に健康状態を管理できるサービスとして打ち出すことができるかもしれません。
このように、常識を疑ってアイデアを生み出すフレームワークとなっています。
4. ワーストアイデア
続いては「ワーストアイデア」です。「常識を疑え」と少し似ていますが、アプローチが異なります。お客様が怒り、信用が大きく傷つくような、非常識で最悪なサービスのアイデアをベースに新たなアイデアを考えるフレームワークです。

手順は以下の通りです。
- まず、最悪な考え方、制約、マナーといったアイデアを洗い出します。お客様が怒り、クレームを入れたくなるような最悪なサービスを考えてみましょう。
- そのサービスが、どうすれば良くなるかアイデアを出します。
例えば、誤った情報が発信されるサービスは、通常はクレームにつながりかねない最悪なサービスと言えます。これを「どうすれば誤った情報が価値をもつか」という方向で考えてみましょう。
一例ですが、消費カロリーを測定する機器が、ときどき実際の消費カロリーよりも少ない数値を表示すると、ユーザーは「今日はあまりカロリーを消化していないので運動しよう」と思うかもしれません。こうして「あえて誤情報を出すことでより健康な生活を促すサービス」というアイデアが生み出せます。
また、操作手順が無駄に多いサービスは、普通は嫌がられますが、これも転換して「複数のスイッチを切らないと止められない目覚まし時計」などを考えれば、「絶対に起きられる目覚まし時計」として売り出すことができるかもしれません。
5. 掛け算・足し算
5つ目のフレームワークは、「掛け算・足し算」です。ここまででマンダラート、635法、常識を疑え、ワーストアイデアでたくさんのキーワードやアイデアが出てきているはずです。これらを掛け合わせ、新しいアイデアに昇華させていきます。
さらに、今まで出たキーワードやアイデアだけでなく、ITを活用した技術要素(例:生成AI、OCR、VRなど)や自社独自の技術やナレッジも掛け合わせて、新たなアイデアへ拡張します。

このように掛け算をしていくことで、今まで出てこなかったアイデアや、面白い視点からのアイデアがたくさん生まれるはずです。
もし、アイデア発散を複数グループで行っている場合、テーブルを回ってさらに拡張してみましょう。
隣のグループのアイデア出しの結果を見ることで、自分たちのグループでは出なかったアイデアが見つかったり、すでに自分たちで出していたアイデアでも、他のグループの視点からさらに深掘りできたりする可能性があります。
また、テーブルを回っている間に新しいアイデアが思いつくかもしれません。そういったものは、どんどん書き足していきましょう。これにより、自分たちのグループでは出なかった発想や知見を、他のグループから得て刺激し合い、アイデアを拡張していくことができます。
テーマの検証
仮に、ここまで紹介したフレームワークを全部実践していれば、1,000を超えるようなアイデアが出てきているはずです。
次に、その中から実際にどのビジネスモデルやアイデアを採用するのか、絞り込んでいく必要があります。
なんらかのテーマをもって方向性を絞り込むことになりますが、まずやってしまいがちな失敗例を紹介します。
失敗例1. 今後拡大していく市場かどうかだけで判断する
例:少子化なので高齢者向けのサービスを考える など
拡大市場を狙うこと自体は悪くありませんが「市場の成長=自社の成功」ではない点に注意が必要です。
例えば、今後間違いなく高齢者向けサービスの市場は大きくなりますが、高齢者向けにデジタルサービスを考えても、デジタルリテラシーが障壁になることが容易に想像できます。
一方で、少子化(縮小市場)の中でも小学生向けのサービスが成功している事例もあるため、市場規模だけにとらわれてテーマを狭めることはお勧めしません。
失敗例2. ひとつの新規事業で失速が見込まれる本業を補おうとする
例:電子書籍の台頭により減った印刷の売上を補うことをゴールとして、全く別分野の事業を考える など
本業に取って代わるような新事業を目指すことは素晴らしいビジョンですが、本業と同規模までビジネスを成長させるには、10年、20年という長期的な努力と忍耐が必要になります。そのため、ひとつの新規事業で本業の失速を補うほどの売上を目標にするのは危ういといえます。
失敗例3. 最新技術を利用することが目的になってしまう
例:とりあえずAIを使って何か事業を考える など
生成AIブームという背景もあり、「とりあえずAIで自動化すればいい」というアイデアがよく出てきますが、技術を使うこと自体が目的化すると顧客のニーズや課題を見落としがちです。AIを使わない方が安くて簡単だったり、AI以外の方法で解決できたりするケースもあるため、技術はあくまで手段であるということを踏まえ、解決すべき課題にフォーカスしてテーマを考える必要があります。
テーマの検証において大事な3つのポイント
先によくない例を挙げましたが、これらも踏まえて、テーマを考える上で大事な3つのポイントを紹介します。
- 何らかの顧客ニーズを満たすもの
- 何らかの社会的課題を解決するもの
- 自分たちがやる意味や強みがあるもの
この3つのポイントに関連して、事例を2つご紹介します。
事例1:株式会社タニタ「タニタ食堂」
株式会社タニタは体重計などの健康計測機器メーカーとして有名です。タニタ食堂は、社員の健康を考慮した社員食堂のメニューを一般にも提供するサービスです。同社の計測機器が利用でき、専門の栄養士によるカウンセリングも受けられます。
- 顧客ニーズ:健康意識が高いユーザーに対するバランスの取れた食事の提供、カウンセリングによる健康増進
- 社会的課題:食事による生活習慣病の予防、栄養士による正しい知識の発信
- 意味や強み:ヘルスケア領域の専門知識、計測機器のマーケティング、ブランドイメージの訴求
事例2:株式会社ベンナーズ「フィシュル」
株式会社ベンナーズは、もともと水産地とバイヤーのBtoBマッチングプラットフォームとしてサービスを開始しました。水産業界で問題となっていた「未利用魚」という、味に問題はないが見た目や傷のせいで一般流通できない魚に着目し、これらを加工してミールキットとしてECサイト販売を行うのがフィシュルというサービスです。
- 顧客ニーズ:調理はしたくないが魚を食べたいユーザーに対するキットの販売
- 社会的課題:フードロスの削減、未利用魚という課題の認知を広げるなどSDGsの観点からの貢献
- 意味や強み:水産業界の知見、産地とのネットワークにより未利用魚を効率的に収集、冷凍保存技術を活用した販売
これらの事例が示すように、テーマ設定においては、「顧客ニーズを満たす」「社会的課題を解決する」「自分たちがやる意味や強みがある」という3つのポイントを押さえることが重要です。
使用者視点の重要性
最後に、補足として「使用者視点」の重要性について少し解説します。
先ほどお伝えした通り、テーマ設定において「何らかの顧客ニーズを満たすもの」が大事なポイントとなります。
しかし、一見顧客ニーズを満たせそうでも、実際にはうまくいかなかった事例も存在します。事業者目線で顧客の課題感を把握しサービスが必要だと考えても、顧客が実際に使ってみると良い体験が得られなかったというパターンです。
そうならないためには、使用者視点によるビジネスモデルの検討や検証が必要となってきます。

「ビジネスモデル検証」では、事業者視点で「どうやったら儲かるのか」「どうやったら認知されるのか」といったビジネスモデル自体を検証し、収益シミュレーションなども行います。一方で、いくら儲かるビジネスモデルであっても、使用者の視点に立った時に「使いにくい」「使う意味があまりない」となってしまえば、結局使われずに終わってしまう可能性があります。
そのため、使用者の視点で「どうやったら使ってもらえるか」「どういうところに本音があるか」を考える必要があります。ビジネスモデルの事業者視点と使用者視点、そのちょうど良いバランスを見つけて、ビジネスモデル自体を調整して検討・検証を進めることが非常に重要となります。
まとめ
ここまでご紹介してきた内容のまとめです。
- ビジネスモデルは非連続では生まれない
– 既存ビジネスとの連続点から見つける
– 自社、あるいは自社周辺のビジネス環境をよく知ることが大事 - アイデア出しは4つのコツを押さえる
– 質より量
– 人のアイデアを否定しない
– 人のアイデアに便乗する
– 会話する、でも一人が喋り過ぎない - 新規事業のテーマは3つのポイントを押さえる
– 何らかの顧客ニーズを満たすもの
– 何らかの社会的課題を解決するもの
– 自分たちがやる意味や強みがあるもの
これらのポイントを押さえて、出てきたアイデアをチェック・検証しましょう。特に顧客ニーズを満たす部分に関しては、使用者視点の検証も重要です。ユーザーの目線に立って、例えばペルソナやカスタマージャーニーマップの作成などを通じて、顧客の本音や真の課題を見つけていくとよいでしょう。
新規サービスのアイデア創出に関するご相談はNCDCヘ
NCDCでは、新規サービス立案ワークショップの標準パッケージをご用意しております。全8回のワークショップを通して、新規事業のアイデア出しから、本セミナーではご紹介できなかった事業性の検討(収益シミュレーションなど)や評価、そしてアイデアを具体化するところまでを行うサービスパッケージです。
新規事業・サービスの立案に課題をお持ちの企業様には、こちらのパッケージをベースにカスタマイズしてご提供することが可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。