NCDCでは、業務システムの導入やリプレイスを検討されているお客様へのコンサルティングサービスを提供しています。
そうしたプロジェクトでは、システムの要件を検討する際に「この業務は特殊だから、今のやり方をそのままシステム化してほしい」「もっと便利になるように、こんな機能を追加できないか?」といった要望が現場からよく挙がってきます。
分かりやすい例として、販売管理システムを考えてみましょう。企業独自の複雑な割引ルールに対応するために「特定の顧客ランクとキャンペーンコードを組み合わせた場合に、特殊な割引計算を自動で行う機能」を追加したとします。
手間のかかる計算を自動化できるため、これは一見、理想的な業務改善に思えます。
しかし、このような機能を実際に導入して運用し続けていくと、その結果はどうなるでしょうか。キャンペーン新設や改訂の度に改修が必要になり、計算ロジックがどんどん複雑化していく恐れがあります。加えて、将来、価格体系を見直す際には「この処理は、誰が何のために作ったんだっけ?」といったブラックボックス化を引き起こしてしまいかねません。
良かれと思ったカスタマイズの積み重ねこそが、業務システムを複雑化・ブラックボックス化させ、システム刷新やビジネス変化への対応を阻む大きな足かせとなるのです。
本コラムでは、例に挙げたような「複雑化・ブラックボックス化」から脱却し、変化に強いシステム基盤を築くための新しい考え方として、SaaSの戦略的活用について解説します。
目次
「SaaSはノンコア業務向け」という誤解
SaaS(Software as a Service) とは、その名のとおりソフトウェアをサービスとして利用する仕組みのことを指し、営業支援・人事労務など特定の業務領域に特化したクラウドサービスが数多く提供されています。
このソフトウェアは多くの企業で成果が実証されたベストプラクティスを標準機能として利用することが前提となっています。そのため、設定変更の範囲内であればカスタマイズは可能ですが、新機能の開発が必要となるような柔軟なカスタマイズは原則として行うことができません。
この特徴から、「カスタマイズ開発ができないので、独自の要件が多いコア業務にはSaaSを利用できない」「SaaSは独自性の低いバックオフィスなどのノンコア業務だけに活用するものだ」という考え方がこれまでの常識でした。
しかし、この考え方はSaaSの可能性を狭めてしまう誤解だといえます。
この誤解を解く鍵は、「コア業務」を2つの要素に分解して捉え直すことにあります。
「Fit&Gap」と「Fit to Standard」
従来のシステム開発では、しばしばFit&Gap分析が行われてきました。Fit&Gapとは、システム(製品)と業務を比較して適合部分(Fit)と乖離部分(Gap)を洗い出す手法です。GapがあればFitする別の製品を探す、製品にGapを埋めるためのカスタマイズを加える、またはスクラッチ開発に切り替える等の対応を検討します。
冒頭で紹介した「販売管理システムに特殊な割引計算機能を追加する」というのもFit&Gapの結果カスタマイズを行う例です。
このように「業務に合わせてシステムを適合させるアプローチ」であるFit&Gapに対し、「標準的なシステムに合わせて業務を適合させるアプローチ」も存在します。それはFit to Standardと呼ばれています。
Fit to Standardは「標準的なシステムに合わせる」という考え方のため、システム開発や運用の面で多くのメリットがあります。
一般的に言われる主なメリットを2つご紹介します。一つ目は、スクラッチ開発に伴う要件定義・製造・テストといった開発工程が不要(あるいは最小限)となり導入期間の短縮・関連コストの削減が期待できる点です。二つ目は、機能改修・新機能開発・セキュリティ対策といった作業をSaaSを提供する企業に任せることでメンテナンス維持費がかからない点です。
しかし、それらメリットを理解していても、実際に「システムに合わせて業務を変えていく」というアプローチを求められると、多くの人は一定のハードルを感じるはずです。それは従来型のFit&Gapによるシステムの検討が主流であり、代替手段のない最善策だという固定観念があるためではないでしょうか。
コア業務を「What」と「How」に分解して考える
そこで、様々ある業務の中でも、特にSaaSが利用できないと誤解されている「コア業務」を以下のように分解して考えてみましょう(ここで言うコア業務とは、企業の競争力の源泉であり、顧客に直接的な価値を提供し、他社との差別化を生み出す「本業そのもの」の活動を指します)。
- 競争力の源泉となる「差別化ノウハウ」(What):企業固有のナレッジ・技術・資産そのものです。例えば、「長年の経験に基づく勘所」「熟練者が持つ技術やノウハウ」「他社と異なる独自のモデル・アルゴリズム」などがこれに該当します。
- コア業務を構成する「業務プロセス」(How):ノウハウを活用し、業務を遂行・管理するための手続きやフローです。「案件管理」「工程管理」「リソース管理」など、「誰が、いつ、何をするか」というプロセス自体は、多くの企業で共通化・標準化が可能です。
「SaaSはコア業務に使えない」という判断は、差別化ノウハウ(What)と業務プロセス(How)という2つの要素を混同しているために生じているケースが多いのではないでしょうか。
SaaSの真価は、汎用性の高い「業務プロセス(How)」の効率化にあります。多くの企業で共通するようなプロセスはFit to Standardを目指すべきといえます。
一方で、企業の競争優位性を生む「差別化ノウハウ(What)」は、フルスクラッチ開発やパッケージ製品※にカスタマイズ開発を加えることによって実現可能になると考えられてきました。
この考え方は間違ってはいませんが、「SaaS利用=差別化を諦めること」ではありません。むしろ、定型的な業務プロセスをSaaSに任せることで、企業は本当に価値のある差別化ノウハウの部分にこそ、貴重なリソースを集中できるようになるのです。
後述するAPI連携やiPaaS活用を前提としたSaaSインテグレーションによって、SaaSのメリットと拡張性・柔軟性の両方を備えたシステムを構築することができます。
※パッケージ製品: あらゆる企業の、あらゆる業務に対応できるように機能が網羅的に用意されていて、オンプレミスで提供されることが多いです。SaaSと異なり、足りない機能があれば、自社の業務に合わせてカスタマイズ開発することが可能になっています。
SaaS活用のコストを適正に図るTCOという考え方
コア業務へのSaaS活用を検討する上で、もう一つの障壁となるのがコストです。SaaS導入を断念してしまう理由として「SaaSは初期開発費用が不要なため安く導入できると思っていたが、長期的な費用を試算すると案外高くなってしまった」という意見をよく聞きます。しかし、システムの価値はTCO(Total Cost of Ownership = 総所有コスト)で判断すべきです。
スクラッチ開発の場合は初期の開発費用に加え、サーバーやクラウドの維持費、そして機能改修のたびに発生する膨大な工数を自社で賄うことになります。特に改修にかかるコストは、元の機能のロジックが複雑であるほど増加していくことになります。これらを考慮すれば、SaaSの方がトータルで安価になるケースは少なくありません。
また、ライセンス形態がユーザー数に依存するSaaSだと社員数に応じた費用増加が懸念される場合もありますが、その業務において本当に全社員が同じようにシステムを使える必要があるのかを精査してみると良いでしょう。案外、数名の担当者にのみライセンスを発行すれば済むケースも多く、費用を抑えることが可能です。
TCOで判断すれば「社員が増えるたびにライセンス発行の手間もかかるし、費用も高くなりそうだから」という考えでスクラッチ開発を選ぶのは、必ずしも得策とは言えないでしょう。
情報を精査せず「スクラッチ開発の初期開発費用と数年分のSaaSの利用料のどちらが高いか」と比べるだけではなく、多角的な視点でコストを比較することが重要です。
SaaSとスクラッチ開発を戦略的に組み合わせる
とはいえ、全ての業務をSaaSに合わせるべきだ、というわけではありません。自社の強みを最大化するためには、先述した業務の「What」と「How」を見極め、他者との差別化ノウハウにあたる「What」を大切にする必要があります。
そのため、システム検討においてはSaaSとスクラッチ開発を戦略的に組み合わせるハイブリッドな視点が不可欠です。※
では、どのような場合にSaaSが適し、どのような場合にスクラッチ開発を選択すべきなのでしょうか。判断基準となる観点は以下の通りです。
※なお、本コラムではSaaSとスクラッチ開発の比較に焦点を当てていますが、両者の中間的な特徴を持つパッケージ製品も、この戦略的な組み合わせの候補になり得ます。
SaaS利用とスクラッチ開発の比較
| 観点 | SaaSが適している | スクラッチ開発が適している |
|---|---|---|
| 優先すべき価値 | ベストプラクティスを業務へ組み込み、市場やビジネスの変化への対応スピードを向上させたい場合 | 独自のサービス体験や技術的優位性を構築し、自社の競争資産として保有したい場合 |
| 対象領域 | 業務プロセス(How)や一部の差別化ノウハウ(What)を、業界標準の機能でカバー可能な場合 | SaaSでは実現・代替不可能な、競争力の源泉となる差別化ノウハウ(What)を実装したい場合 |
| 柔軟性 | 提供される機能と設定の範囲内で、迅速に業務プロセスを構築・変更したい場合 | 将来の拡張や変更を見据え、制約なく自由にシステムを設計・開発したい場合 |
| 開発期間 | 迅速にシステムを導入し、早期に価値を享受したい場合 | 時間をかけてでも、要件を完全に満たす独自のシステムを構築したい場合 |
| 保守運用 | 法改正対応やセキュリティ対策、機能更新などをベンダーに任せ、自社の負担を軽減したい場合 | 機能改修や更新のタイミングを、外部に依存せず自社で完全にコントロールしたい場合 |
| 許容可能なリスク | ベンダーへの依存や、業務を標準機能へ適合させるコストを許容できる場合 | 技術的負債の発生や開発の長期化、変化への対応が遅れるリスクを許容できる場合 |
これらの判断基準を踏まえて、具体的なケーススタディを見ていきましょう。
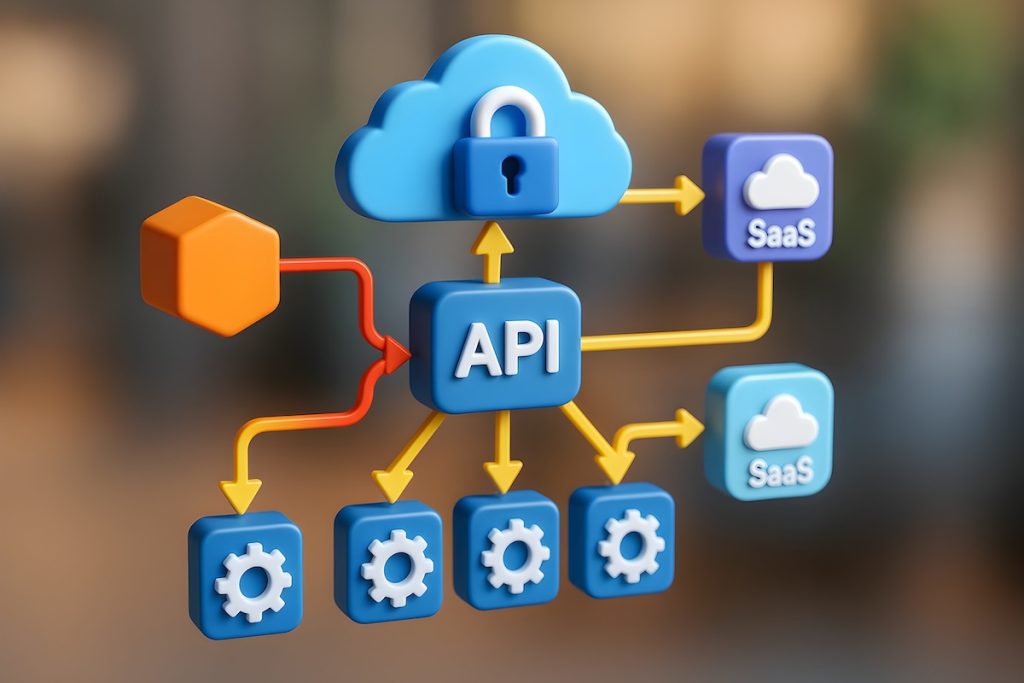
ケーススタディ1:属人化したプロセスの標準化を目指す製造業
システム化検討の背景
この企業は当初、熟練工のノウハウをAI化したシステム構築を目指していましたが、開発の複雑さとコストの観点から計画は頓挫しました。この失敗から、真の目的はAI化という手段ではなく「ノウハウの形式知化」であると再定義。AIによる完璧な自動化よりも、まずはSaaSを導入して迅速に業務を標準化することから始めると決断しました。
システム化のアプローチ
- 業務プロセス(How) → 戦略的SaaS導入: 生産計画、工程管理、リソース管理といった業務プロセスは、生産管理SaaSを導入して標準化。データに基づいた改善サイクルを回せる体制を構築します。
- 差別化ノウハウ(What) → SaaS機能を活用した形式知化: 熟練工のノウハウ(目視による判定、加工条件の微調整など)は、無理にAI化・自動化しません。SaaSのチェックリスト機能やナレッジ共有機能を活用し、「人が判断すべき項目」として形式知化します。
ケーススタディ2:独自のマッチングモデルを持つ人材紹介会社
システム刷新検討の背景
この企業では、長年運用してきた独自のマッチングシステムが老朽化し、リプレイスが急務でした。ただし、前回のシステム開発時に経験した開発の長期化や技術的負債の発生といったリスクは避けたい状況です。そこで、差別化の核となるマッチングのアルゴリズム部分のみ独自で構築し、その他は原則としてSaaSに任せるハイブリッドな刷新アプローチを採用することを決断しました。
システム化のアプローチ
- 業務プロセス(How) → SaaS活用: 求職者の情報や選考進捗を管理する採用管理システムや、顧客企業を管理するCRMといった業務プロセスは、SaaSを全面的に活用して標準化・効率化します。
- 差別化ノウハウ(What) → スクラッチ開発: 競争力の源泉である独自のマッチングアルゴリズムはスクラッチで開発。SaaS上の求職者・求人データをAPI経由で取得し、最適なマッチング結果を算出します。
SaaSインテグレーションで、システムの価値を最大化する
複数のSaaSや独自開発のシステムを導入しても、それらが独立して存在しているだけでは不十分です。データの二重入力やシステム間の情報分断は、単なる手間の問題に留まらず、情報の信頼性を損ない、ビジネスにおける意思決定の質を低下させる致命的なリスクに繋がります。
この「情報の分断」という課題を解決し、価値を最大化するために不可欠なのが「連携」という視点です。ここでは、SaaSインテグレーションを実現するための3つの重要な技術を紹介します。
APIによる「システム間の連携」
連携を前提とする以上、SaaS選定で最も重要な基準の一つがAPI(Application Programming Interface)です。APIとは、システムの機能やデータを外部から利用するための仕組みです。
例えば「在庫管理SaaSのAPIに条件を渡すと、条件に合致した商品の一覧を返してくれる」というように、値を渡せば期待する結果を返してくれる窓口として振る舞い、そのSaaSの「在庫を検索する」という機能自体を呼び出すことが可能になります。
選定するSaaSの機能自体が優れていても、外部システムと連携するためのAPIが貧弱ではハイブリッドなシステム構築は実現できません。APIドキュメントが整備されているか、十分な連携実績があるか、といった観点での評価が極めて重要になります。
iPaaSによる「データの連携・自動化」
iPaaS(Integration Platform as a Service)は、プログラミングをせずとも異なるSaaSやシステム同士をAPIでつなぐことができ、データの流れを自動化するハブの役割を担います。
例えば「営業SaaSで顧客情報が登録されたら、その受注確度を基にマーケティングSaaSの対象リストを更新するAPIを呼び出す」といった自動連携が可能です。
これは、二重入力を防ぐような単なる効率化ではなく、整合性のある信頼性の高い情報を、部門や組織を横断したリアルタイムな共有を促進し、顧客への対応スピードや質を向上させるなど、「攻めのIT」の基盤となります。
MCPによる「AIと業務システムの連携」
MCP(Model Context Protocol)とは、異なるSaaSやシステムに蓄積されたデータを、AIアシスタントがコンテキスト(文脈)を保ったまま横断的に解釈・活用するための共通規格です。
営業用のシステムと顧客サポートのシステムがMCPを用いてAIと繋がるという構成が実現すると、例えば「先月のA社との商談履歴と、直近のサポート問合せ内容を要約して、新規商談だのための提案書ドラフトを作って」とAIに指示するだけで、営業SaaSと顧客サポートシステムから必要な情報を収集・統合し、瞬時にアウトプットを生成してくれる、といったことも可能になります。
昨今ではMCPへの対応を発表するSaaSも増えています。執筆時点ではまだ発展途上であり精度も高くないかもしれませんが、将来を見据えると、SaaSを選定する際の基準の一つに加えても良いかもしれません。
まとめ:SaaSに対する考え方をアップデートする
SaaSは、コア業務のシステムにも活用することが可能です。そのためには「SaaSはノンコア業務向けであり、コア業務は自社専用で独自に作るべきだ」という従来の固定観念をアップデートすることが重要です。
- コア業務を「差別化ノウハウ(What)」と「業務プロセス(How)」に分解して考える
- 「業務プロセス(How)」にはFit to Standardを適用してSaaSを積極的に活用する
- 「差別化ノウハウ(What)」にはSaaSとスクラッチ開発を組み合わせ、独自の競争資産を構築する
- 優先すべき価値や許容可能なリスクなど踏まえて、SaaSとスクラッチ開発を効果的に採用する
- APIやiPaaSを活用し、SaaSを含むシステム同士を柔軟に連携させる
SaaSは単なる便利ツールではなく、ベストプラクティスとも言える優れた業務プロセスをFit to Standardで迅速に取り入れることを可能にしてくれます。また、SaaSを上手に活用することよって生まれたリソースを差別化領域に集中させることは、ビジネスの成長を加速させることに繋がります。
NCDCは、本コラムでご紹介したような戦略的なシステム構想の策定から、SaaSの選定支援、SaaSとスクラッチ開発を組み合わせたハイブリッドなシステムの設計・開発・導入まで一貫してご支援することが可能です。自社のシステム戦略に課題を感じていらっしゃいましたら、ぜひ一度、私たちにご相談ください。






